鉄製 鋼製仕様ではマメな塗装 メンテナンスが必要
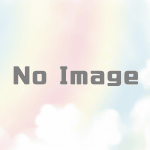
横浜市港南区の「K」様邸の鉄骨階段部分です。鉄骨階段がリフォームで取付けられてから
五年しか経っていないそうですが、年数では錆の進み具合がひどいと感じます。
錆び止め塗装が足りないか薄かったのかなと思います。
バルコニー鉄骨円柱修理補修では鉄骨職のはやり廃りを知る
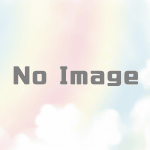
横浜市港南区の「K」様邸のバルコニー柱鉄骨職の修理が終わりました。
塗装の順番では、鉄骨修理 → 錆び止め → 仕上げ塗装。という順番になります。
いままでは鉄骨職が塗る錆び止め塗装は赤いもの。という考えでした ...
雪で曲がってしまった軒樋を交換するには
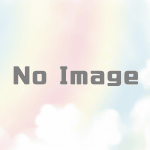
横浜市港南区の「K」様邸の軒樋です。こちらの「K」様邸は一部マンサードタイプの
屋根になっていまして、以前の大雪の時に雪が落ちる時に勢いで曲げてしまったという事です。
施主様の種々のご都合で今時になってしまいま ...
ひどく腐食したバルコニー鉄製柱を取り替えるには
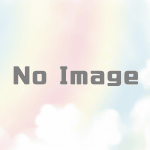
横浜市港南区の「K」様邸のバルコニー柱の部分です。鋼製円柱が錆で断面欠損が50%程度あります。
この後施主様が、この円柱周囲を手摺下から笠木上までコンクリートで根巻きされましたので、
上下方向の力には耐えられま ...
三豊百貨店の現象を思い出す梁型のヒビ
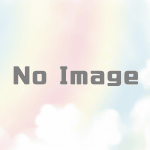
横浜市港南区の「K」様から、バルコニー部柱の交換についての見積もり依頼を頂きました。
築年数もあり、大分錆が進んでいます。自分が気になったのはこの部分です。
この写真ではつぶさに見えませんが、壁と直角方向、柱に ...