【修理】瓦屋根の修理では
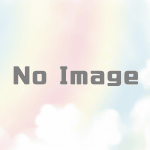
横浜市戸塚区の「Ko」様から瓦屋根の修理を依頼されました。
築年数が経っていることもありますので屋根周囲が痛んできています。
屋根部分で傷みやすいのが、軒先ケラバ破風です。
その中でも以前の仕様で木 ...
【雨戸修理】外壁修理と雨戸戸袋修理では
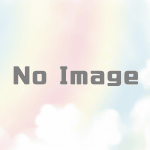
前回依頼を頂いたおりに、外壁の塗装と雨戸、雨戸戸袋の塗装をしたのですが
雨水、湿気の関係で下地のベニヤが剥がれてきました。
戸袋鏡板(戸袋の表面の板の事)を腐らないケイカル板(通称:ケイ酸カルシューム板)で
木造住宅のメンテナンスと修理の事を書いています。
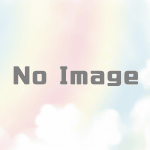
横浜市戸塚区の「Ko」様から瓦屋根の修理を依頼されました。
築年数が経っていることもありますので屋根周囲が痛んできています。
屋根部分で傷みやすいのが、軒先ケラバ破風です。
その中でも以前の仕様で木 ...
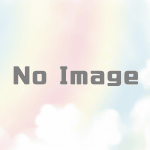
前回依頼を頂いたおりに、外壁の塗装と雨戸、雨戸戸袋の塗装をしたのですが
雨水、湿気の関係で下地のベニヤが剥がれてきました。
戸袋鏡板(戸袋の表面の板の事)を腐らないケイカル板(通称:ケイ酸カルシューム板)で